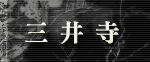

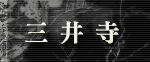 |  | ||
|
|
|||
|
|
〔今回のテーマ〕記憶、証言、歴史 もし世の中の出来事を、すべて言葉によって説明できたり、映像技術によってリアルに再現しうると考えるなら、 小説を書いたり、絵を描いたりする、従って、芸術を創造する切実な必要性はないであろう。
1).
もうずいぶん以前のことになってしまったが、
クロード・ランズマン監督の映画『ショアー』に接した時の衝撃は今でも忘れることができない。
夜中に何気なくテレビをつけた時、偶然にも放映されていた映像に釘付けになってしまい、
食い入るように見続けた。ヘブライ語で「絶滅」を意味する『ショアー』は、
ナチによるユダヤ人などの絶滅収容所の記憶、いわゆるホロコーストを描いた映画である。
九時間三十分に及ぶこの大作は、記録映像などを一切使わず、
十一年に及ぶ歳月をかけて制作当時生きていた人たち(証人)を探し出し、
彼らの回想(証言)だけによって構成されており、八五年にフランスで公開されるや大きな反響を呼んだ。
日本では、なんと十年遅れの九五年になってようやく上映された。
ところで、同じテーマを扱った過去の表現作品の多くが、
ホロコーストという出来事(経験)を過去の悲惨な歴史と云った、ぼくたちが了解し易いような完結した物語として、
いわば「神話化」されて語られてきた。
こうした事情を岡真理氏は『記憶/物語』(岩波書店)のなかで適切に述べている。やや長くなるが引用しておきたい。
「絶滅収容所という極限状態においてさえ人間はかくも崇高でありえた、
いかなる暴虐も人間の魂の尊厳までは奪えなかったというような物語を欲しているのは、誰だろう。
それは、絶滅収容所というものを直接体験することのなかった者たち、〈出来事〉の外部で生きている者たち、
すなわち私たちが、安心してこの世界の日常を生きながらえるために、必要としている物語なのではないだろうか。
〈出来事〉の内部の、私たちには窺い知れない、想像を絶した暴力が、〈出来事〉の外部、
すなわち私たちの世界によもや侵入してこないように、私たちを不安にさせないように。
そこで語られているのは、〈出来事〉の記憶ではない。それは、私たちの物語、私たちのファンタジーの投影だ。
私たちが〈出来事〉の記憶を分有し、それを私たちの記憶にするために語られた物語ではない」
まさに、ぼくたちは、如何に取り返しのつかない多くの〈出来事〉について「ページをめくって」きたことか。
これに対し、映画『ショアー』は、常軌を逸した未曾有の出来事にあっては、
たとえそれを体験した人であっても、すべてを言葉では語り尽くすことはできないということ、
それが物語化されるや忽ちそこから漏れ落ち、排除され、あるいは忘却されてしまう事柄があること、
そして、日常の言葉では語り得ない出来事を伝えるとはどういうことか、といった戦争の記憶、
証言にまつわる様々な問題をぼくらに問いかけてくる。
その意味でもスピルバーグ監督の『シンドラーのリスト』の対極に位置する記念碑的な作品として、
ひときわ特異な光彩を放っている。
2).
「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ではないが、過去を振り返って苦しくつらい経験であっても、
今から思えば良い思い出であったと思うことは日常茶飯のことであろう。
戦争など社会的な記憶についても事情は同様である。ぼくたちの記憶とは常に現在からみた記憶にすぎないし、
歴史にしても客観的な歴史といったものは何処にもなく、どこまでいっても「修史」にすぎない。
こうしたことを痛感させられたのは、九一年八月、
金学順(キムハクスン)さんが元日本軍従軍慰安婦であったことを最初に名乗り出たことであった。
その後、それまで声を抑えられていた戦争被害者が歴史の「証人」として一斉に立ち現れ、
戦後半世紀を経て、あらためて戦争の「記憶」が呼び覚まされた。
他方、こうした動きに逆行して、南京大虐殺はなかった流の歴史修正主義、
西尾幹二、藤岡信勝、小林よしのり各氏など「新しい歴史教科書をつくる会」による
日本人のマジョリティーに標準をあわせたナショナリスティックな言動が跋扈している。
しかし、個人の顔と名前をもった証人の証言に真摯に耳を傾けようとしない否定論は、
死に等しい体験を強いられた証人を、もう一度殺すに等しいことになるのではないだろうか。
今回は『ショアー』を導きの糸として記憶と証言、そして歴史について考える著書をとり挙げてみたい。
さて、今日でも絶大な影響力をもつ写真論と云えばヴァルター・ベンヤミン『複製技術時代における芸術作品』、
ロラン・バルト『明るい部屋』、スーザン・ソンタグ『写真論』であるが、
その他にもジョン・バージャーや日本では多木浩二氏、伊藤俊治氏、飯沢耕太郎氏などの仕事が思い浮かぶ。
3).
まず第一に、記憶とは、コンピューターのように符号化されて貯蔵され、
必要に応じて検索され引き出されるような情報ではないということである。
ぼくらの記憶とは現在の情動や前後関係によって、現在に適合されるように構築される現在であり、
現在に適合されるように築かれる過去なのである。

写真家としてユニークな活動をされている港千尋氏の『記憶』は、
「記憶とは創造である」という命題をめぐって芸術家や思想家の様々な表現を通じて幅広い思考を展開している。
固定化された痕跡としての記憶は存在しない。 記憶とは創造的な構築あるいは再構築であり、 過去の経験や反応に対してわれわれがとる態度や感情と切り離して考えることはできない。
ことに、ジャコメッティと彼のアトリエをミニチュア再構成した
作品で知られる異才マットンを扱った「回想の力」、
映画『イル・ポスティーノ』にも登場するチリの詩人パブロ・ネルーダと
彼の名前を冠した写真集を出版したルイス・ポアロについての「写真と不在」の章など
「記憶」にまつわる刺激的な内容に満ちた書となっている。
4). 
高橋哲哉氏の『記憶のエチカ』は、
ハンナ・アーレントの読み込みを通じて『ショアー』を本格的に論じた「記憶されえぬもの、語りえぬもの」が
収められており、歴史を忘却や隠蔽から救い、歴史修正主義に対峙する思想家としての立場を明確に主張している。
〈われわれの現在〉のうちにはけっして現前化しえない過去との関係、 〈われわれの現在〉によってはついに記憶されえず、「忘却の穴」に沈んでしまった過去との関係によって 〈われわれの現在〉がたえず異化され、他化されるような歴史性を考えなければならないのだ。 〈われわれの現在〉の自明性を徹底して疑問に付すことが必要である。
ぼくら戦争を知らない世代が物語として聞かされてきた戦争の歴史を徹底して疑問に付すこと、
歴史が「修史」として整えられ物語化される一歩手前に立ち返り、
語りえぬものを語りえぬままに保持している場所に踏みとどまることが何よりも必要である。
語り得ぬものを物語=叙述(histoire)の仕方で語ることはあくまで不可能だろう。 ランズマンが、それでもなお〈不可能な〉証言を証人たちに要求していくとき、 証人たちが断片的に発するいくつかの言葉が、物語=叙述としては挫折するまさにそのことを通じて、 語りえぬものをかろうじて示唆しているように思われることである。
証言の断片化を意味の分からないものとして切り捨てることなく大切にすること。
戦争という暴力の記憶を忘却することは、何よりも記憶への暴力なのである。
5).
イタリアのユダヤ人家庭に生まれたプリーモ・レーヴィは、アウシュビッツの生き残りである。
四五年一月二七日、ソ連軍によって解放された彼は同年十月一九日に生まれ故郷のトレノに帰り着く。
この九ヶ月に及ぶ帰還の旅は小説『休戦』に描かれ、邦題『遙かなる帰郷』として映画化されており、
ご覧になった方もおられるであろう。
さて、故郷に戻った彼は四七年、レ・ウンベルト街の自宅で『アウシュヴィッツは終わらない』
(原題『これが人間か』)を書く。この著作は『アンネの日記』、フランクルの『夜と霧』、
エリ・ヴィーゼルの一連の著作とともにナチについての証言文学として今も世界中で読み継がれている。

徐京植(ソキョンシク)氏『プリーモ・レーヴィへの旅』は、日本語を母語として育った在日朝鮮人である著者が、
アウシュビッツの生還者であるレーヴィを自らの分断された生に重ね合わせながら
トレノにある彼の墓を訪ねる旅の紀行である。
著者がレービィと出会ったのは、著者の二人の兄が朴政権下の韓国へ「母国留学」中に
政治犯として投獄された時であった。この間の事情については、
著者自身が編んだ岩波新書に収められた『徐兄弟獄中からの手記』に詳しい。
さて、こうした著者にとってレーヴィとは、アウシュビッツ以降「人間」という理念の廃墟に生きるわれわれが、
なお生きていけるという「尺度」そのものであったという。
ところが、解放後四十数年を経て、結婚し作家としても成功していた六十七歳のレーヴィは、
長年暮らしてきたアパートの四階の手すりから階下のホールに身を投じた。著者の「尺度」が死んだのである。
「レヴィが一九八七年に自殺しなかったならば、すべてが単純明快であっただろう」。
ブルガリア出身の知識人ツヴェタン・トドロフがそう書いている(『極限に面して』)。
いわばこの言葉に引きずられるようにして、私はこの旅に出たのだ。
ぼくたちは、著者と共にレーヴィの死を深く考えてみなければならない。
その時、遙かトリノから日本と朝鮮に至るまで世界中に充満している
歴史の犠牲となった人たちの悲痛な叫びを聞き取ることができるかもしれない。
いまこそ耳を澄ますときである。
(園城寺執事 福家俊彦)
<< 写真、写真論 | 詩人・石原吉郎(前編) >>
・「二十一世紀の図書館」に戻る ・「連載」に戻る |