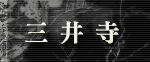

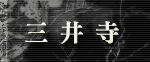 |
 |
||
|
|
|||
|
|
〔今回のテーマ〕失われた時を求めて(その二) プティット・マドレーヌの味から「失われた時」が目覚め、無意志的記憶が積み重なって大聖堂となる。二十世紀文学の頂点プルーストを読む。(後編)
1). (承前) 一九六五年のクリスマス、雪のパリ・オルリー空港に一人の女子学生が降り立った。ジュリア・クリステヴァ、二十四歳。枯葉色のスーツケース二つ、ポケットには五ドルしか入っていなかった。当時はまだ鉄のカーテンの向こ
う側、東欧ブルガリアのユダヤ系家族のもとで生まれ育った彼女は、やがてフランス知識界に衝撃を巻き起こすことになる。ロラン・バルト、リュシアン・ゴルドマンの指導のもとに瞬く間に頭角を現し、六九年には画期的な論文集『セメイオチケ』を出版。バルトの記号論的視点とラカンの精神分析的視点を結びつけた独自の言語・文学理論は、今日に至るまで重要な問題を提示し続けている。
当時のパリは、バルト、ラカンの他にもフーコー、デリダ、バンヴェニストなど名だたる思想家、作家たちが割拠する知の最前線であった。時代も実存主義から構造主義へ、六八年にはあの「五月革命」を経験する、まさに知が沸騰した時代でもあった。やがて彼女は、前衛文学の旗手であった作家フィリップ・ソレルスと結婚、彼と共に当時を象徴する雑誌『テル・ケル』を導いたことはあまりにも有名である。
2). さて、クリステヴァが提示した世界とは、如何なるものであろうか。
近代思想は、われわれの生きる世界が科学的にも日常的にも主体と客体によって構成され、「理性」を用いて「認識」できる世界であることを理論化してきた。だから、科学的真理は世界中に妥当し得るし、人間は、男や女、或
いは人種を異にしようとも同じ「人間」として平等であるという理念を掲げることが可能となった。
また、ある社会に生きる個人にしても、例えば、ぼくならば日本に生まれた「日本人」として、また「女性」でなく「男性」として、子供からは「父親」、両親からすれば「息子」として、その他様々な社会関係が束になった存
在として、ぼく自身のアイデンティティを保持して日常生活を送っている。
それは取りも直さず、われわれの世界なり社会が、例えば、日本にあっては日本語の椅子という言葉が、腰をかける椅子を意味するように、あらゆる面にわたって、ひとつの「言語」として、記号・意味のシステムとして構造化されていることを意味している。われわれが自分のアイデンティティを保持して日常を生きていけるのも、この世界が、言語=文化によってコード化(規範化)された「コスモス」を形成しているからである。
3). もし世界が徹頭徹尾、静謐で整然としたコスモスであれば、何ら問題はない。少なくとも文学や芸術はたいした意味を持ち得ないであろう。
ところが、ぼくたちは、こうした世界の構造から溢れ出してしまう《過剰》をつねに抱えこんでいる。
いつの時代にも、その社会に生きる普通の人にとってはごく当たり前の社会規範に対して、適応できずに精神を病む人は存在してきたし、また英語の「man」が「男」であると同時に「人」一般を意味するように、社会や言語によって「人間」の理念が、ひそかに「正常」な「男」を規準に考えられてはいなかったであろうか。言語・記号によって秩序づけられたわれわれの社会は、その社会が「正常」と見なす規準から外れるものを、例えば精神病、性倒錯などと名付け、異常なものとして片隅に追いやり、あるいは外国人、女、子供といった存在にマイナス符号を付してきた。
だから、こうした存在について、すでに構造化された社会において、通常の、従って「正常」で「男」の側に属する言語をもって語ることは、本当は非常に困難なことである。今日問題になっている「ひきこもり」や「登校拒
否」なども通常の言葉では到底読みとることができない問題領域に属する事柄であることを言う人は少ない。
しかし、社会に適応している大部分の人でも、例えば、恋愛などによって、それまで安定していたアイデンティティが一挙に揺らぎ出すことがある。こうした限界的体験を通じて、普段は意識しなくても、自分の中に様々な欲動
や情念が渦巻いており、自分で自分をコントロールできないカオスをかかえ込んでいることに気付かされる。恋が狂気の沙汰と言われる所以である。
4). クリステヴァの関心は、一貫して、通常の社会から《過剰》なものとして排除され、社会の周縁に追いやられた、いわばマージナリティ(周縁性)を有するものに注がれている。
彼女は安定した社会関係、言語と主体からなる秩序(コスモス)を《サンボリック》と名付け、これを突き崩し解体する力を《セミオティック》と名付けた。こうして恋愛なら恋愛という体験をサンボリックとセミオティックのせめぎ合うカオス的な状態、彼女の用語ではシニフィアンス(記号・意味の生成)のプロセスとして記述してきた。それは言語が言語として定着する前の様々な情念や欲動などが沸き立って決定不能な状態、理性による認識の対象となる以前の、いまだ《名づけえぬもの》を通常の言語によって記述するという至難な試みであった。
ここで注意すべきは《名づけえぬもの》、セミオティックなものは、社会的秩序(サンボリック)を通じてしか発現しないという点である。詩的言語といっても、通常言語と全く別の特別な言語が存在するわけではなく、あく
までも通常の言語によって、その言葉の音楽性の強調や統辞法の破壊などを通じてしか表現され得ない。それは、フロイトが解明したように「無意識」がそれ自体として直接把握できる訳ではなく、「言い間違い」や「夢」といった「意識」面を通じてしか顕現しないのと同じ事情であろう。
5). 
さて、彼女は九〇年に自伝的小説『サムライたち』を発表した。本書は、激動の時代、多くの知のサムライたちと共に第一線の知識人として膨大な仕事をこなし、また恋をし、やがて母となっていく自らの半生を回想風に再創造
した作品である。
その冒頭、彼女がパリに来て最初に出席する講義が、バルトによるプルーストである。また、夫となるソレルスと共に過ごす大西洋の小島、白い砂丘で読むのも『失われた時を求めて』である。こうして彼女の半生を通じて親しんできた思いが熟成し、大部なプルースト論となったのが『プルースト感じられる時』(九四年)である。
本書は、彼女が築き上げてきた多くの理論的営為、記号論、テクスト論、精神分析、女性論、芸術論などを駆使してプルーストを論じた理論書であるというよりは、これらの知見の化肉である彼女自身が、まるごと全身で長い時間をかけてプルーストと語り合った対話の記録と考えた方がよい。

だから読者は、普通の文学研究書を読む場合とは違って、プルーストとクリステヴァの言葉が反響しあって、二人のテクストが溶解し相互浸透を起こし、「テクストはすべてもうひとつの別なテクストを吸収、変形したものである」とする彼女の《間テクスト性》の思考へ誘い出される。
あのでこぼこした長さ、あの終わりのない、それでいて慎ましやかな息づかい、記憶を試練=試し刷りにかけるあの従属節、論理の枝分かれを前にしたときのわれわれの精神の機能不全を補う、あの畳韻法の音楽・・・
と述べられるプルーストの文章は、サンボリックとセミオティックのせめぎ合う接合点から発せられた言葉、透明で中性的な言語から排除される様々な《過剰》を積極的に引き受けた言語実践(エクリチュール)に他ならない。
ここに、あの大容量の小説を支える生命力の源泉があるのである。
いまだ時間となる前の時、言語となる前の原=言葉、意識に現れる無意識、理性に把握不可能なもの、これらを如何に言語に移し替えるかをプルーストは生涯を費やして求め続けた。彼がこの小説に刻みつけた「失われた時」と
「見出された時」、マドレーヌ菓子に象徴される「無意志的記憶」、文学や音楽、絵画などの諸芸術の意味も、いつにこの点にかかっているのである。
6). このことと関連して、彼女の師であり盟友であったロラン・バルトに言及しておきたい。いまは『新=批評的エッセー』に収められた論文「プルーストと名前」である。この小文は、プルーストのエクリチュールにとって重要な位置を占めるコンブレーやゲルマントといった小説に登場する固有名詞の 機能について論じている。

実は、固有名詞とは言語学的には特殊な性格をもつ品詞として多くの議論がなされてきた。例えば普通名詞の「女」という言葉(シニフィアン)は、現実に存在するすべての女性に共通する属性を抽象してできた概念(意味=シニフィエ)に対応している。これに対して「アルベルチーヌ」という名は、アルベルチーヌという名のすべての女性の共通の性質を意味しているわけでなく、ある特定の「アルベルチーヌ」という女性を直接に指示しているにすぎない。固有名詞が「シニフィエなきシニフィアン」と言われる所以である。
「固有名詞」はいわば無意識的記憶の言語形式なのである。したがって、『失われた時を求めて』を《発進させた》(詩的)事件とは、「名前」の発見ということになる。
クリステヴァを介して述べてきたプルーストのエクリチュールと固有名詞は分かちがたく結びつき、われわれの前に開かれた世界を提示しているのである。
(園城寺執事 福家俊彦)
<< 失われた時を求めて(その一) | 9.11以後 >>
・「二十一世紀の図書館」に戻る ・「連載」に戻る |