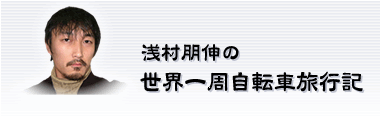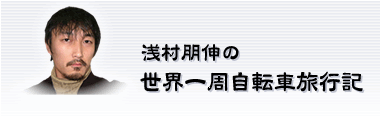僕はマンハッタンを抜け出して、いよいよ、アメリカ横断を始めた。西へ向かうにはどうすればいいのだろう、と思っているとインターステイツという高速道路に出た。46号線から、北に向かう206号線に乗り換え走り続ける。地図を確認すると絶望的な大きさだ。まずはイリノイ州到達まで始めの4分の1が勝負だ。そこまで行けば後は何とかなるはずだ。
スクラントンの町に着いてマクドナルドに入り、ビックマックを食べていると閉店だと言われた。暗くはなっていたが、そんな時間でもないだろう、と思って時計を見ると、まだ6時である。クリスマスだからなのか理由はわからないが、とにかく、閉店と言われたので急いで店を出て自転車に跨った。6号線は自動車専用道に変わり、どこを探しても回り道は見つからなかった。仕方が無いので大きな坂を下って町の中の住宅街へ抜けて行くと、どの家も、競って派手なクリスマスの電飾を飾り付けていた。さて、6号線はどちらになるんだろう?と思いながら住宅街をさまよった。地図がなければ回り道などを見つけられない。とにかく地図は持っておいたほうがいいだろうと思って、スーパーで地図を買うことにした。レジで地図代を払おうとすると、隣の男が地図代を払ってくれた。クリスマスだからなのだろうか、自転車旅行が珍しいからなのか、とにかく親切は非常に有り難い。
スーパーの店員に道を訊いて、言われた方向に向かっていると、再び迷子になり、道を確認するためにガソリンスタンドに入ったが、店員が道に詳しくなかったので、仕方なく出発しようとすると、スタンドの売店で買い物をしていた男達が30ドルをくれた。クリスマスということもあるのだろうが、この辺りのアメリカ人は他人に対して、随分、親切に振舞ってくれる。自転車を押して町を歩きながら、すれ違った散歩中の男性に6号線への道を訊ねると「さあ、わからないな。君は今日どこに泊まるつもりだ?」と聞かれた。とりあえず、6号線に出てから野宿できる場所を探すつもりだというと「もし、泊まる所がないのなら、我家に泊まりに来ればいい」と言って、彼は僕を家に案内してくれた。彼の家に着くと、奥さんは、いきなりの来客に困った表情をみせた。無理もない。いきなり、旅行者が泊まりに来たら、困るのは当たり前だ。
「いいじゃないか、今日はクリスマスなんだ」
そう言って彼は奥さんをなだめた。
僕は、シャワーを借りた後、ビールを飲ませてもらった。
「肉は冷めたようだからレンジで暖めよう」
彼はクリスマス用の肉を食べさせてくれた。さっきまで迷子になって途方に暮れていたのに、彼が、ビールと肉を振舞ってくれたおかげで、思いがけず、クリスマスの気分が味わえた。彼は9月11日のニューヨークのテロについて語りだした。
「アメリカとは一体どういう国なのか、我々、アメリカ人自身が考えるきっかけになったと思うのだよ。君は一体、どうしてイスラム教徒のテロ組織にニューヨークが狙われなければいけなかったと思うかね?」
「中東にあるイスラエルとオイルにアメリカが関与するからでしょう」と答えると
「我々がイスラエルを支援するのは、聖書に書かれていることを信じているからなんだ」と彼が言ったのを聞いて僕は、少しびっくりした。
「我々は知るべきなのだ。アメリカは完璧ではない」
彼は真剣な顔で言った。そんなことはアメリカ人以外の誰もが知っている、と彼に教えてあげたかった。
朝になって出発の準備をしていると
「ビールを持っていきたまえ。それと肉も」
そう言って彼は2本のビールとアルミホイルに包んだ肉をくれた。
「6号線まで案内しよう」
彼は車で6号線の入り口まで先導してくれた。
「ここでお別れだ。体に気をつけて頑張れよ」
僕は彼に礼を言って、6号線を走り出した。別れた地点から、さほど遠くないところにあったガソリンスタンドでコーヒーを買った。セルフサービスのコーヒーをカップに注いで金を払い、外に出て道路を眺めながらゆっくりとコーヒーを飲んでいると(やれそうだ。頑張れば何とかなるんじゃないか)という気分になった。隣で同じようにコーヒーを飲んでいた男が「どこへ行くんだ?」と聞いてきた。
「ロサンゼルスへ」
「この自転車でかい?」
「そうさ」
「気は確かかい?」
「もちろん」
空は晴れきっていた。道もはっきりとつかめた。やれないという気は全くしない。必ず、ロサンゼルスまで走れる気がする。気は確かだった。
順調に6号線を走り続けていると、次第に辺りが暗くなってきた。どこかでテントを張ろうと適当な場所を探したが、ポツンポツンと家が点在しているせいで、いい場所を見つけてもテントを使えそうにない。
アメリカには、あちこちに広い林があるのだが、必ず柵が張り巡らせてあり、中に入れないようになっている。それに10m程の間隔で木に「個人所有につき立ち入り禁止」の張り紙が、林が続く間、何百、何千と、神経質に張られている。もし、柵を乗り越えて中にいるところを発見したら撃ち殺すぞ、と言わんばかりの念のいれようである。ヨーロッパだったら林の中に家があるなんてことはあまりないし、柵を張り巡らせているなんてこともないので、テントを使用するには断然ヨーロッパの方が楽である。道路の片側が林のある土手になっていたので、そこでテントを張ろうと思って、よじ登り下見をしてみた。丘の上ならテントを発見されることもない。テントの張れるスペースがあったので、丘の上に自転車と荷物を数回に分けて登った。僕はテントを張って、蝋燭を灯し、昨日もらった肉を食べながらビールを飲み、クリスマスを一人で祝った。
朝、スーパーで買い物をしていると、アメリカ人が話し掛けてきた。
「私はさっき車の中から君を見たんだ。よかったら、君を家に招待したいんだ」
僕は彼の申し出を受けるかどうか、考えた。どうせ朝から雪が降っているせいで、あまり距離は走れないはずだし、少しくらいゆっくりしてもいいだろうと思った。僕は彼の招待を受け入れることにして、自転車で車の後について行った。雪の降る林を抜けて辿り着いた彼の家にはかわいらしい女の子がいた。私が彼女を教育しているのよ。と奥さんは言った。
「学校へ行かずに?」
「そうよ、この子は学校へ行ってないわ。」
「アメリカでは、そういうのは結構あるのですか?」
「あるわ」
「この子に何か日本語を話してくれないかしら」と奥さんは言った。
「あなたの名前はなんですか?」と僕は女の子に向かって話し掛けた。
奥さんは難しそうな顔をしている。
「どうかしましたか?」と僕は彼女に訊ねた。
「宣教師というのは不思議な力で、異国語も理解できると言われているの。私はそれを試してみたかったの」
「それで、日本語は理解できましたか?」
「いいえ、残念だけど。私は、まだまだ努力が必要なのよ」
夕食を食べさせてくれた後で、彼は僕をモーテルに送って行ってくれた。モーテルとは車の駐車場に部屋が面したドライバー用のホテルだが、自転車旅行だろうと普通に利用することができる。
翌朝、彼は車でモーテルに来て朝食代だといって10ドルをくれた。彼は気をつけて、と言って見送ってくれた。昨日、彼と出会ったスーパーに行って、ボールペンを買った。今まで使っていたペンのインクがなぜか出てこないのだ。町の中を走っているとハンターの店があった。ここなら何か役に立つ物があるかも知れない。中に入ってみると予想通り防寒具が揃えてあった。とはいえ、こちらには金がない。安くて実用的なものであれば、買ってもいいが、高い物を買ってしまうと大陸横断はそこで終わりだ。ゆっくりと店内を見回していると、靴の中敷を発見した。これがあれば多少は足底の冷えが違うに違いない。僕はワラにもすがる思いで購入を決めた。そうだ、足なのだ。一番の問題は末端だ。すなわち、手先と足先。
僕は無謀にもトルコで買った革靴を履いて自転車で走っていた。いくら、ドイツでシューズカバーを買って被せてみたところで所詮、防寒靴にはかなわない。足先が凍傷になっては大変なので厚手の靴下も買うことに決めた。これだけ分厚ければ全然違うだろうと思うぐらい分厚い。僕は店を出ると、その場で靴に中敷を入れた。中敷を入れた上に、靴下が分厚いので、靴をはくのが大変だった。やっとの思いで、苦労して靴を履いてみたのに、冷たさはそうたいして変わらない。
「所詮、こんなものか」
やっぱり、この寒さは尋常ではない。その時、ふとあることを思いついた。新聞を靴に巻きつけて、その上からシューズカバーをかぶせれば、新聞が防寒効果と保温効果を発揮するかもしれない。僕は早速、靴の上に新聞を巻きつけ、その上にビニールを被せてシューズカバーを履いた。さらに、もう一度、その上に新聞をかぶせ、ビニル袋をかぶせ、フランクフルトで買った二つ目のシューズカバーをかぶせた。結果は期待通りの防寒効果を発揮した。これで、寒さも怖くない。金がなくても何とかなるものだ。
夜中になりテントを張る場所を探してみたが、なかなか見当たらなかった。辺りはすでに暗くなってきていた。ふと気が付くと道路から林道のような細い道が伸びている。林の中へ入っていけるに違いない、と思って木々に挟まれた細い道を雪を踏み分けて、奥へ進んでいくと、一軒の物置小屋のようなものがあり、そこからさらに進んでいくと完全に林になっていた。そこまで行くと、道路を走っている車からは見えないだろうと思い、林の入り口にテントを張ることにした。
テントの中で食事を済ませ、眠る準備をしていると、何やら、外で騒がしい車の音がした。人が来たとなると面倒だなと思っていると、いきなりサーチライトでテントが照らされた。何事だ?と驚くと「出て来い」とスピーカで叫んでいるのが聞こえた。テントのファスナーを降ろして外をのぞくと、数台のサーチライトと、数人の警官が僕に銃を向けているのが見えた。
アメリカではちょっとでも怪しいそぶりを見せた場合、発砲しても正当化されるということを思い出した。怪しいそぶりを見せるな、落ち着け、と自分に言い聞かせ、ゆっくり両手を挙げた。警察はこちらに来いとスピーカで叫んでいる。「わかった」と言って外へ出ようとすると、テントの中に靴を置いていることに気がついた。後ろを向いて靴を取ろうとしたその時、「動くな!動くと撃つぞ」と言う大声がした。さらに「出てこないと撃つぞ!」と大声で繰り返している。僕は慌てて「靴だ!靴を履きたいんだ!」と何度も叫んだ。「わかった」と言う声を確認して僕はもう一度、後ろを向いて靴を探した。一言でも聞き間違えたら射殺されてしまうかもしれない。僕は靴を履いて両手を挙げながら「今からそちらに行く」と言って、銃を向けている警察の方へ歩いていった。
日本人であることを告げ、自転車でロスに行くところだと説明したが、彼等は理解できていないようだった。どうやら、テロリストと間違えられている。彼らは僕のパスポートを調べ、怪しいものではないと分かると、旅の目的を聞いてきた。アジアからヨーロッパまで横断して、これからアメリカを横断するところだと説明すると彼等は驚いたようだった。どうやら、小屋には誰かが住んでおり、テントを不審に思って警察に通報したらしかった。テロが起こってから住民はナーバスなんだ、と警官は言ったが、彼も相当ナーバスに見えた。
これまでに体験したことの無い寒さだった。視界は吹雪で閉ざされていた。吹き付ける雪に逆らいながら進んでいくしかない。立ち止まると足を地面につけるだけで痛い。刺すように冷たい。寒い。とにかく寒い。どうにかなってしまいそうなぐらい寒い。手足は完全にシバレていた。耐寒グローブはあったが、そのままでは全く役に立たなかった。それでも足先と足底は冷え切っていて刺すように痛い。指が動かず、ハンドルバーを握ることもできない。ちぎれそうな痛みに耐えて、握り締めた拳でハンドルバーを押さえつける。アメリカの自然が僕の行く手を阻んでいた。雪が吹き荒れる峠の坂道を登っていく。歯を食いしばれ!僕は自分に言い聞かせた。
「止まるな、必ずここを突破するんだ!」
思うように進めない。容赦なく吹雪が殴りつける。誰があきらめるか、と唱えながらペダルを踏み込んでいく。何となく待っていた気がする。確かに、このときを待っていた気がする。これが海外旅行だ。これが自転車旅行というものなのだ。そう思うと、苦痛は苦痛ではなかった。
日が沈んで、野宿する時間になったので、僕は林の奥に自転車を持っていった。昨日のこともあったので、民家とは離れた所でテントを張ろうと思い、林の中を自転車を押して進んで、民家の明かりが見えないところまで距離をとってテントを張った。夕食を済ませ、蝋燭を消して寝ていると、外から車の音と「出て来い」という大声がした。蝋燭は消してから随分、時間が経っているのに、また見つかってしまったのか、やれやれ、と思い、出て行こうとすると、テントの前で「ズダーンッ!」という発砲音がした。
「俺は銃を持っている。おとなしく出て来い!」と叫び声がした。
僕は慌てて「今からテントの外へ出るから撃つな!」と3回叫んだ。テントの入り口のファスナーを降ろして顔を出すと、僕の額に銃口を向けて立っているアメリカ人が二人いた。僕は膝をついたまま、ゆっくりと両手を挙げた。
「何をやってるんだ」
「自転車でアメリカを横断中で、宿に泊まる金が無いから野宿している」
「パスポートを見せろ」
パスポートを見せると、彼等は戻ってくるから待っておけ、と言って立ち去ってしまった。パスポートを他人に渡したのはマズかったが、この場合、下手に拒否して、気が高ぶっている彼らの神経を逆撫でするより、手渡した方が安全だろうと思った。パスポートなんて命をかけて守るものではない。テロリストではないということがわかれば問題は無いだろう。30分程して、彼等はザクザクと足音を鳴らしながらテントの前に帰ってきた。テントから顔を出すと、彼等はパスポートを差し出しながら「ここで寝ると寒いだろう、俺の家に来るか?」と訊いてきた。
「いや、構わなければ、ここで寝かせてくれないか?」と僕は言った。
今からテントをたたんで、自転車に荷物を積みなおして移動するのは面倒臭かった。
「寒くないのか?」
「寒さには慣れているんだ」
僕は、パスポートを受け取って再びテントの中で眠りについた。
朝になって、走り出すとガソリンスタンドが現れたので、靴の上に巻きつけるための新聞と、コーヒーを買って飲んだ。そして、モーテルに泊まった翌日に買ったペンが、また使えなかったので、新品のペンを買った。
さすがに二日連続で、野宿を発見されてトラブルが起きると、精神的に疲れが出る。こんなことを繰り返しているわけにはいかない。かといって、これから先で似たようなことが起こらないという保障はないのだ。危険なのは誤解を招くことだ。テロが起こってアメリカ人は神経質になっている。家々に掲げられている星条旗は、アメリカ人がテロに屈しないことを皆で表明しているというが、まるで悪魔払いのおまじないのように見える。星条旗さえ掲げていればテロリストはやってこないと信じているように見える。勇気づけるというよりも何かに脅えているようにしか見えない。そんなところへ、不審な人物が現れると誤解を招くのは必然だ。ましてや、有色人種で英語が少ししか通じないとなると、余計に誤解を生じてもおかしくは無い。
予想通り、買ったばかりのボールペンは全くインクが出なかった。なぜアメリカのボールペンは、どいつもこいつも使い物にならないんだろう、と腹が立った。アメリカを横断し始めてから、野菜不足になるのを一番恐れていたが、スーパーで、いいものを発見した。ドールから発売されている野菜の詰め合わせパックである。キャベツやレタス、それにニンジンなど数種類の野菜が細切れにされている。これさえあれば野菜不足にならずにすむ。パンにマーガリンを塗って、野菜を挟んで食べるだけでいいから時間も節約できる。野菜と牛乳さえあれば、そうそう体を壊すことはない。カチカチに凍った野菜をシャキシャキとかじり、マーガリンを塗ったパンに挟んで食べた。
日暮れになって、川沿いにキャンプ場のような公園を見つけた。ここなら、テントを発見されても不審感は薄いだろう、と思ってテントを張ることにした。公共の土地だけあって、いくらか落ち着いて寝ることができた。
僕は売店で、ラジオの電池と、蝋燭に灯をつけるためのライターと一緒に日本製のペンを買うことにした。日本製は割高だったが、無駄な出費を重ねるわけにはいかない。しかし、使用してみると日本製のペンは、今までのものと同じくインクが出てこなかった。なぜだ?日本製なのに・・・。ひょっとして寒さでインクが凍っているのか?僕は、ようやく原因に気がついた。バカバカしい。僕はボールペンを体温で温めるために腹巻の中に入れて走るようにした。結果は予想通りで、上手く使えた。何しろ、ペットボトルのジュースを買っても二時間後にはカチンカチンに凍って飲むこともできないほどの寒さである。ボールペンのインクだって凍って当たり前なのだ。
夕方になって国立アレゲニ森林公園という大きな森に差し掛かった。国立公園なら少なくとも、個人所有ではないので、役人や警察以外には文句を言ってくる者はいないだろう。森林の奥なら見つからずにテントを張れるはずだ。
僕は薄暗くなりかけた森の中に入って行った。森は延々と続き、途中で道が別れていたりするので、地図を持たずに入ると確実に迷子になりそうだった。地図で道を確かめながら進んで、真ん中辺りに差し掛かったところでテントを張ることにした。テントの中で蝋燭を使うとテントがボーッと明るく灯って目立つので、道路を走る車から見えない森の奥の方の位置まで自転車を押して行き、テントを張った。
車のライトは遠くかすかに見えているだけである。テントから光が漏れないように、バッグで蝋燭を隠し、凍える手で食パンにマーガリンを塗って食べながら地図を確認した。もうじき五大湖に到達しそうだった。五大湖まで行けばルート66を見つけられるはずだ。トラブルは続いているが確実に前進している。雪に覆われた森の中で無事に新年の朝がやって来た。平穏に朝が迎えられることが、こんなに気持ちのいいことだとは思ったことがなかった。僕は国立アレゲニ森林公園を抜けて再び6号線に戻って走り続けた。
年が明けて二日目、出発してすぐに、ガソリンスタンドで牛乳と新聞を買い、スタンドで新聞を広げながら牛乳を飲んだ。新聞に書いてあることは、いつもテロとブッシュ大統領の話題である。新聞を広げて牛乳を飲んでいると、人並みの生活を送っている気がして、一日がスムーズに進みそうに感じる。300$でアメリカを自転車で横断すると言っても、考えてみれば、一日、一日は何も、たいしたことをやっているわけではない。パンを食べながら自転車に乗っているだけなのだ。
寒さに耐えながら、僕は、とうとうオハイオ州に入州した。州境の湖にかかっていた橋を渡ると、水は全部凍っている。本当に寒い。スーパーの入り口で、何気なく、アメリカの子供用に作られた絵本があったので、手にとり、パラパラと、中をめくって見て愕然とした。その塗り絵には、アメリカの国旗や偉人、国鳥である鷲が描かれており、どのページにも「アメリカは正義である」とか「アメリカは強い」とか「アメリカは平等だ」「アメリカは自由だ」「素晴らしいアメリカ」といった文句が並んでいた。どう考えても子供を洗脳しているとしか思えない。そういうことは、それぞれの人間が自分で様々な基準をもって判断するものだ。アメリカ人は愛国心が強いと言うが、こういうものに小さい頃から囲まれて育ったのなら、それは愛国心ではなく、洗脳教育の結果じゃないのだろうか、という気がした。
野宿地を探していると、キャンプ場があった。明らかにシーズンではなく閉鎖されている。果たしてテントを使ってもいいのだろうか?後で、話がややこしくならないようにキャンプ場の前にあった家の住民に、キャンプ場でテントを使うことを知らせ、そこで雪の中にテントを張って野宿した。
クリーブランドクリーブランドの町まで来ると雪は無かった。町は都会だったが、人通りが少なく寂しげだ。とはいえ、ビルを見るとホッとする。ここまでくれば、あの狂いそうな寒さに悩まされることも無い。今まで使っていた地図の範囲が終わり、これからは五大湖沿岸を走るので、新しい地図を買った。ここから、しばらく山越えをする必要は無いので、スピードが上がることを期待できそうだった。ペンシルバニア州の積雪地帯でペースが遅かった分、この先、取り返せるところで取り返しておきたい。
ロサンゼルスはまだ遥か彼方だが、なんとなくアメリカ横断の最初の壁は突破できたような気がした。 |